
こんにちは、山キャン情報室 管理人の亀太郎です。
誰でも一度は耳にしたことのある「そこに山があるから」。
イギリスの伝説の登山家マロリーの残した名言ですが、男女にかかわらずロマンを感じますよね~
でも、その言葉の本当の意味って、意外に知られていません。
ここでは、「そこに山があるから」を英語でいうと、マロリーの名言の意味が分かってくるので紹介します。
- この記事を書いている人
登山歴:2007年~キャンプ歴:1995年~ 
- 九州の大学卒業後、愛知県の自動車会社で車体構造の研究に従事する傍ら、1995年からデスクワークのストレス解消にオートキャンプを始める。
2007年からは、「山頂でテント泊をしたい」との単純な発想から、登山を独学で学び(一時期、山岳会に所属)、今はソロテント泊主体に活動中。
そんな経験もふまえ、大手メディアでは取り扱っていないノウハウや小ネタ情報を発信しています。
「そこに山があるから」の英語「Because it’s there」からマロニーの名言の意味を考えてみた
名言の始まりは1923年3月18日付けのニューヨーク・タイムズの記事から

この言葉は、1923年3月18日付けのニューヨーク・タイムズのマロニーへのインタビュー記事から始まります。
何度もエベレストに挑戦するマロリーに記者が質問。
- 記者「Why did you want to climb Mount Everest?」
- マロリー「Because it’s there.」
日本語に直訳すると
- 記者「なぜ、あなたはエベレストに登りたかったのか?」
- マロリー「なぜならば、そこにそれがあるから」
っとなりますが、「それ」の「it」って何でしょう?
その解釈の仕方で意味が全く変わってきます。
解釈1:「Because it‘s there」の「it」は「エベレスト」

「なぜ、あなたはエベレストに登りたかったのか?」との質問に答えたので、「Because it‘s there」の「it」は「エベレスト」と考えるのが妥当。
そう考えると、こんな会話だったと予想されます。
- 記者「なぜ、あなたはエベレストに登りたかったのか?」
- マロリー「そこにエベレストがあるから」
ん?
マロリーは、単純に「当時は人類未踏峰だったエベレストだから登りたかっただけ」なの?
解釈2:「Because it‘s there」の「it」は「山」

「Because it‘s there」の「it」を、抽象的な「山」と解釈してみると、こんな↓感じ。
- 記者「なぜ、あなたはエベレストに登りたかったのか?」
- マロリー「そこに山があるから」
山は、人生と同じ。目先に捉われず、その山の頂上を目指し、何も考えずに一生懸命のぼればいい。
それが、充実した人生を過ごす秘訣なのだ。って哲学的な話に解釈も成立する。
では、どっちの解釈が、正しいんだろう?実際、何十年にわたって解釈論争が続いたようです。
「そこに山があるから」は世紀の大誤訳だともいわれている
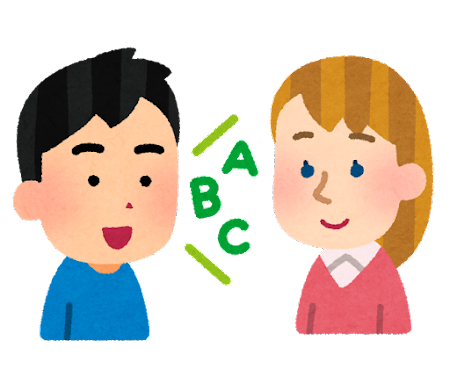
現在は「そこにエベレストがあるから」説が優勢
2005年に「そこに山があるから登るという世紀の大誤訳」という表題で発表された論文が出されました。
それを要約するとこんな↓感じです。
- 「そこに山があるから」は日本における世紀の大誤訳のひとつであろう
- 「マロリーが答えたのは、『エベレストに登る理由』であって、単に『山に登る』という一般的行為に対する回答ではない
あらら(;^_^A
当時は誰も登ったことがないエベレストに登りたくなるのは、登山家として当然のことだ… と言っているに過ぎない様です。
歴史に残る名言は誤訳によって生まれることもある
「名言の正体」という論文にはこんな↓風に書かれています。
- 歴史に残る名言は誤訳によって生まれることもある
- マロリーのこの言葉は、その最たる事例と言えるだろう
- エベレストを登る意味を尋ねた記者の質問への回答としても「山」と答えるのは的外れ
マジですか(@_@;)
山男のロマンじゃなかったようですね(笑)。
でも、「そこに山があるから」は名言として解釈したいっ

生前のマロリーを知っている友人も「そこに山があるから」について、書籍で「この言葉は少しもジョージ・マロリーらしい匂いがしない」と書いているようです。
でも、別の書籍にはこんな↓記述も。
- もし彼自身がそれを口にしなかったとしても、この言い回しは、彼という人間とエヴェレストを征服せんとの彼の情熱的な追求を完璧に要約している
- 「そこに山があるから」はマロリーの墓碑銘として永遠に残るだろう
ふむふむ。
何か難しいことをやる時に非常に高い壁があったとしてもそれをやりたくなる。誰もやったことのないことへの人間の本質的な欲望。
いずれにしろ、「そこに山がある」っていう名言は、色あせることはないと思いますよね~
まとめ
以上、「そこに山があるから」を英語でいうと、マロリーの名言の意味が分かってくる内容を紹介しましたが、いかがでしたか?
その言葉の本当の意味が分かっても、「そこに山があるから」っていう名言は、色あせることはないと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

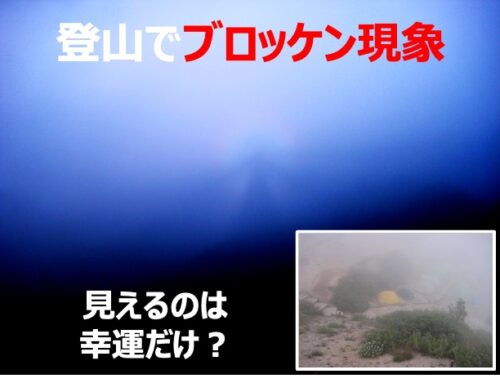
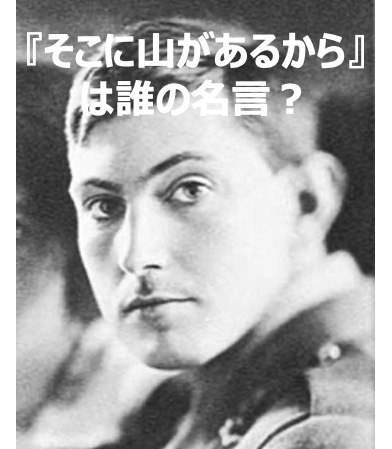
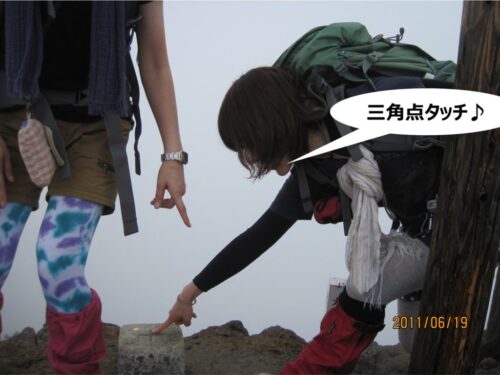
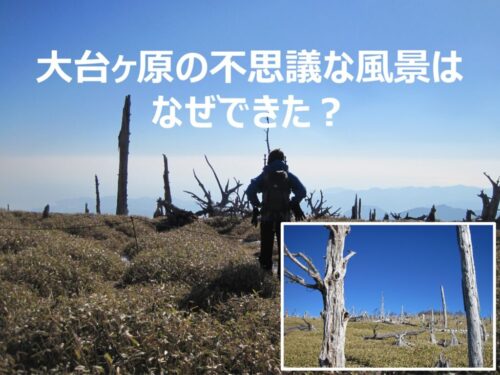

-e1614307144330.jpg)